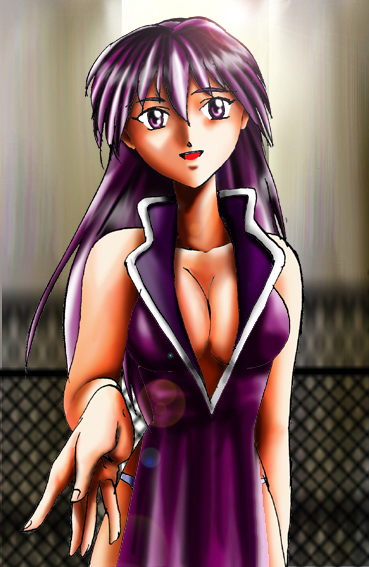ネガイ
k
殺し屋なんて、所詮屑以下の存在だ。
そう思っていた。今でもそう思っている。
じゃあ何故お前はこんなことをやっている?
他に生き方をしらないから。
目の前を通り過ぎた拳に無表情に掌を添え、外からの蹴りを繰り出す。
ベキィッ
乾いた音が響いて、腕一本折られた男は苦痛に顔をゆがめた。そんなものに興味はない。残像が残る速さで体を回し、側頭部に蹴りを放つ。
ゴキッ
何度聞いてもいやな音。頭蓋骨陥没をしたかもしれない。だけど、そんなことより確かな音。
相手の命が消えた音。
静かに佇んで目の玉が飛び出さんばかりに見開かれた相手を見た。全身のGを足に乗せて繰り出した蹴りは重く相手に衝撃を与える。吹き飛ばしたりはしない。その分のパワーを全て相手の体に叩き込む。もしかしたら、脳みそは砕けているかも知れない。
ゆっくりと力を失い、倒れていく相手にあたしは無言で背中を向けた。
どうしようもない掃き溜めのスラム。あたしはそんな場所で育った。親はいない。「マリー」という名前も、周りが呼ぶからそうなのかと思うだけで、本当の名前がなんなのかはしらない。
親がいないから、本当の名前も存在しないのかもしれない。
ロリコン親父に体を売り、かっぱらいやすりをやることであたしはどうにかここまで生き長らえてきた。どうしようもない屑。ハイソサイエティな人たちから見たらあたしってそんな存在。だけど、そんな屑に汚れ仕事を頼むあんたたちってどうなのよ?
そんな矛盾した疑問と、それでもそれによって得られる報酬であたしは強くなっていった。
人はあたしをこう呼ぶ。"Bloody Mary"(血まみれの聖母)
j
ヒトハドウヤッタラスクワレルノ?
j
教会から出てきたあたしを、いつも仕事を持ってきてくれるブローカーのマイクが捕まえた。
「よう、今日も神頼みか?」
「別に。頼むことなんてないわ。それより何の用?」
隣を歩くマイクがちびたタバコに火をつける。スラムの朝は寒い。吐いた息かタバコの煙かわからないようなもので空気を染めながらマイクが口を開いた。
「日本からヒットマンのスカウトがきてんだ。どっかであんたの名前を聞いたらしい。破格の待遇らしいぜ。」
「日本から?」
わざわざ海を越えて?ばかばかしいことをするやつがいたものだと思った。だが、正直言ってそういうものに興味はない。あたしは首を横に振った。
「そうか。ならトビーにまわすぜ。あんたの後釜狙ってるからな。やる気満々だ。言えばすぐにテストを受けるだろうさ。」
「テスト・・?」
あたしは思わず足をとめてマイクを見た。殺し屋を雇うためのテスト。そんなの聞いたこともない。
「ああ、何でも丸1日サバイバルらしいぜ。」
・・・丸1日のサバイバル・・・?
「どういうこと・・?」
「24時間、奴さんの飼い犬と戦うらしい。」
「・・・めんどくさいことすんのね。」
止めてあったバイクに跨って緩くウェーブする金髪をかきあげた。あたしのバイクを取ろうなんて馬鹿はこの辺にはいない。とっても命と引き換えだからだ。
「まあ、あんただったらそのテストもなかったらしいがな。」
「まあ、トビーなら大丈夫でしょ。またましな仕事があったらよろしく。」
あたしはそう言い残して、バイクの爆音とともにねぐらへと走り出した。
k
イッタイダレガサバイテダレガユルストイウノダロウ?
k
ぼろい薄汚れたアパート。そこの3Fをぶち抜きにしたのがあたしの城だった。マイクと別れてふと思い出した用事を済ませた頃には夕方になっていた。その頃にはあたしはスカウトの話なんかすっかり忘れていて、今日の夕飯を誰にたかるかを考えていた。
ケニーは金持ちだけどへたくそだし・・・ジョイはまだ給料日前だしなあ・・・。ロイが確か昨日稼いでたとか言ったような気がする。うん。ロイにしよう。
バイクを降り、上への階段を上り家の鍵をポケットから取り出す。古ぼけたドア。いくつも並んでいるそのドアの、本当に使っているのは一つだけ。あたしはそのドアの前に立ち、鍵を差し込もうとして違和感に気づいた。
「・・・!?」
かすかに漂う錆びた鉄の香り。もう嫌だと言うほど嗅ぎ慣れたこの香りをあたしが間違えるわけはなかった。あたしはドアとは反対側の壁に身を隠し、鍵を開けるとノブを回し陰に隠れたままドアを開けた。
キィ・・・・タンッ
目の前をきらめく刃が走り抜け、勢いよく反対側の壁に突き刺さる。
「ほう・・・さすがに勘はいいようだな。」
面白げな声。その声に神経をおろし金ですられるような感じを受けながらあたしは開いたドアの前に音もなく立った。
リビングとして使っているその部屋は、血の匂いと硝煙の匂いが充満して普通の女の子なら吐き気を催してしまいそうな有様になっている。
あたしはドアに手をかけ、壁にもたれるように声の主を見た。
黒髪黒目。チャイニーズかと思ったそれにしてはなんだか雰囲気が違う。長い髪を無造作に一つに纏めて男は立っていた。着古したTシャツによれよれのジーンズ。手にはS&W38口径。その足元には、手足をことごとく折られ、どてっぱらを打ち抜かれて死んでいるトビーの姿があった。
「・・随分手ひどいじゃない?」
思わず眉を顰めたあたしに男は妙なイントネーションの英語で言った。
「ボスが、手加減無用だって言ったからな。」
「・・・どういうつもり?」
「何、俺たちの仲間になって日本へ一緒に帰ってくれりゃあいい。」
ここにいたってあたしはやっと昼間のマイクの話を思い出した。
「・・・トビーは何時間でやられたの?」
あたしの問いに男は軽く肩をすくめた。
「3時間ってとこかな。まあ、俺たち相手によくがんばった方だと思うよ。」
「そう。じゃあ断るわ。」
あたしの言葉に男が苦笑を浮かべた。
「おいおい・・冗談だろ?」
「別に。トビーに3時間もかかる相手に使われる気はないって言ったの。」
見る目に男が気色ばむ。
男達の狙いはこうだ。お前もこうなりたくなかったら一緒に来い。
自分たちより弱いヒットマンをスカウトに来たつもりでいるんだろうか?そんなんじゃ意味がないだろうに。
「・・・どうしてもこないってのか?」
「お断りよ。もっとましなやつが出てきな。」
ふんと馬鹿にして笑うあたしに男が手に持った拳銃を構えようとした。それよりも早く。
タンッ
男の額にあたしが投げたナイフが突き刺さる。
「ナイフ使いならわかるかと思ってたんだけど・・。3アクションのガンよりナイフの方が早いってね。」
小さく呟くとあたしはそのまま一気に走り出した。
ガシャーンッ!
窓を勢いよく突き破り、向かいの店の屋根に飛び移る。そのまま飛び移った街灯を伝って路上に降り立つとバイクとは別の方向に駆け出した。
男がえらそうにしゃべっている間にも二つの気配が階段を上って迫っていた。男は「俺たち」と言った。ならば数はそれなりに揃えていると考えるべきだろう。外にも気配は一つ。合計3つの気配をあたしは感じ取っていた。外の気配はとてつもなく強い。だが、この気配が動いていないということは恐らくトビーをやったのは後の3人だ。
ということは残るは二人・・・。
あたしの喧嘩は我流だ。そしてあたしを追ってくる者達は間違いなく手練。さっきのナイフにしても、怒りを誘って意をつかなければああもあっさりとはいかなかっただろう。
あたしは路地を抜け、できるだけ人気のない細い裏路地に飛び込んだ。
k
ダレガミチビキイキサキハドコ?
k
一見無謀とも思えるが、この路地の先は普段子供たちが3オンをやるちょっとした広場になっている。路地を走るあたしの後ろに殺気が生まれた。
「・・・!」
とっさに身をかがめてやり過ごすと髪を掠めるようにナイフが飛んでいく。そのまま大きく前転をして進み、見えた金網に一回手をかけただけであたしは飛び越えた。着地ざま横に転がるとサイレンサーのくぐもった音とともに地面に小さな土煙が舞う。
「・・なかなかやるみたいだな?」
「そりゃ・・・さっきの腑抜けと一緒にしないで欲しいわ・・。」
あたしを追ってきた二人が金網の扉を開けて入ってきた。
一人は東洋系の顔のくせに金髪で黒スーツで手にはコルト。もう一人は黒いジーンズの黒いTシャツで無手。
トビーは足が速く、裏をかくのに長けていた。だから3時間も持ったんだと思う。だけどあたしは逃げ回るのは趣味じゃない。
「手短によろしく。」
そういうあたしに金髪の男が笑った。
「もちろんだ。」
それを合図に無手の男が動いた。
ひゅっ。
軽く風を切って足が右から飛んでくる。軽く後ろに引いてかわすと今度は足払いが飛んでくる。これも軽く飛んでかわし、あたしは距離とスピードを計った。次々に中段下段と襲いくる蹴りをかわしていくと、必然的に右端に追い詰められる形になる。
「終わりかい?」
ふっと男が笑うと、唐突に左からのフックが飛んできた。
「ちぃっ!」
あたしはこれを飛んで衝撃を殺しながら右腕で受ける。今まで足攻めできたのはこれが狙いだったのだ。腕にジーンと痺れが走る。だがあたしは、伸びきった相手の腕を掴むと、そのまま体に捻りを加えて投げ飛ばした。そのまま男が受身を取る前に容赦ないローキックを頭部に叩き込む。
ゴキッ
「ぐぇ」
いやな音と、悲鳴が同時に上がった。
地面に落ちてきた男の足を踏みつけて折り、掴んだままの腕を捻って腱を引き千切り肩から外す。これで万一気がついたとしても戦線復帰はできない。・・・恐らくその必要性はないだろうが。
「・・随分容赦ねえな・・・。」
見ると金髪男がコルトをぶら下げたままあたしを見ていた。
「あんたたちもトビーに容赦なかったでしょ?」
あっさりとそういうとあたしは男と対峙した。さっきの無手の男よりは強い。そう思える殺気。
ザッ
男が動いた。コルトを構え、ぴたりと照準をあわせてくる。
「何!?」
男が驚愕に僅かに目を見開く。無理もない、あたしは男に向かって突っ込んでいったからだ。
「自信家だな!」
パスッ!
「違うわ!」
男のコルトが火を噴く。銃弾が撃ち出されるときのほんの少しのぶれ。あたしが狙っていたのはそれだった。照準が合わせられた弾丸から逃れることは難しい。ならば・・・。
ばっとあたしの左肩が紅く染まるそれでもあたしの動きはとまることがなかった。男が次の激鉄を起こす前にあたしは男の胸倉をつかみ、太腿のガーターベルトからすばやく抜いて顎の下にコルトオートマチック22口径を押し当てた。
「うぐぅ・・・・。」
「ゲームセット。試合終了ね。」
この位置から打ち抜けば、いくら銃が小さいとはいえ間違いなく脳を貫通する。それで全て終わるはずだった。
「・・・!?」
とっさに男を突き飛ばして飛び下がらねば、今、あたしの腹にはナイフが刺さっていたことだろう。そのナイフは、地面にしっかりと突き立ち、かすかに振動を残していた。
「くっ!」
慌てて周囲を見回すと、いつの間にいたのか随分と派手ないでたちの女が立っていた。長い髪に露出の高いチャイナドレス。その女は、薄い笑みを唇に湛えて金網に凭れていた。
「そいつまで殺されたら・・・・さすがに少し困るの。優秀な人材は一人でも欲しいのよ。」
最後の一つの気配の正体。あの大きな気配はどうやら彼女だったらしい。あたしは血の吹き出す肩を押さえて女を睨みつけた。
「そんなに怖い顔をしないで。ただ、スカウトに来ただけだから。」
女は、くすりと笑うと長い髪をかきあげた。
「断ったら?」
「そんなにお馬鹿さんじゃないでしょ?」
「頭はよくないわよ・・・。」
緊張に冷汗が背中を伝う。あたしは、じりじりと移動しながら女をじっと見つめていた。一触即発の空気が流れる。
ザッ!
「Go!」
最初に動いたのはあたしだった。流れるように一気に距離を詰め、そのまま背後に回りこむと回転を利用して横から蹴りを叩き込む。
「What's!?」
ドカッ!ズザザザザザッ
軸足を払われ、あたしはわけもわからないうちに地面を滑っていた。跳ね上がって身を起こそうとしたあたしの顔面に鋭いナイフの切っ先が突きつけられる。スピードもさることながら、そのパワーも凄まじいらしい。足払いを受けたあたしの軸足は、腱の断裂を起こしかけてずきずきと痛んでいた。
「Shall we go?」
微笑みとともに女があたしを見た。

「・・・・ふぅ・・・。」
小さなため息をつくとあたしはその場にあぐらをかいて座り込んだ。
「日本にはハラキリっていうのがあるそうね?好きにすればいいわ。」
女はにっこり微笑んで再度言った。
「Shall we go?」
「・・・・Yes」
あたしはこう答えるしかなかった。だけど不思議といやな気分はしなかった。
「ありがとう。決して悪いようにはしないわ。」
微笑んで差し出される手を取ってあたしは立ち上がった。
「Yes,Boss.あたしは・・知ってると思うけど’マリー’。あんたは?」
女はにっこり微笑んでこう言った。
「My name is Akemi Rikutou.」